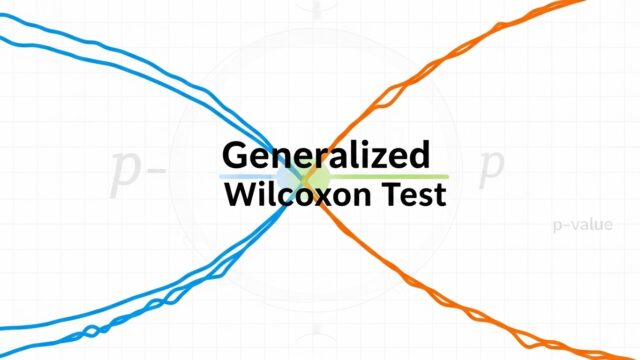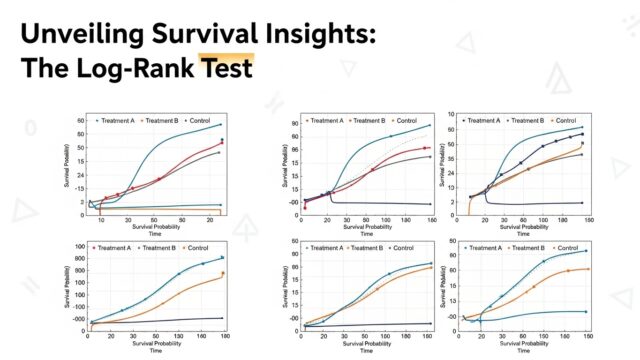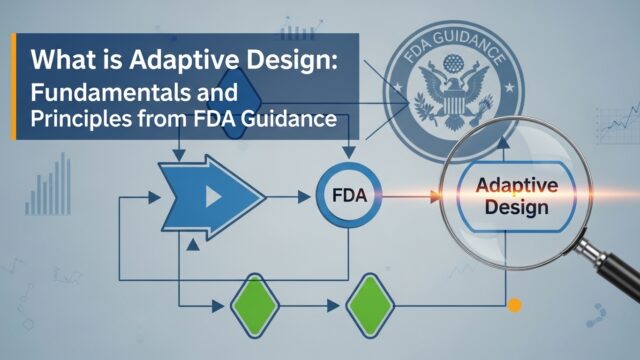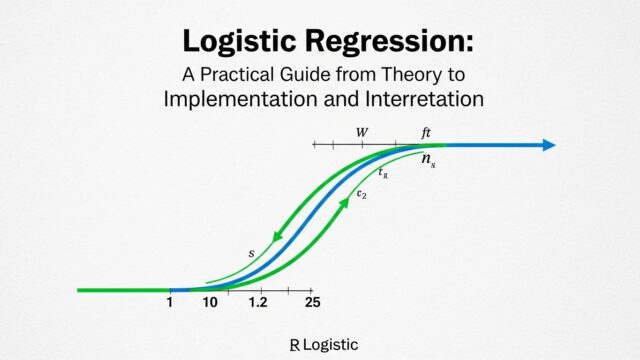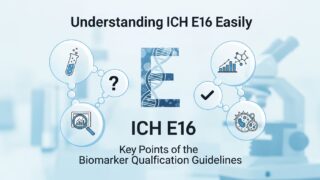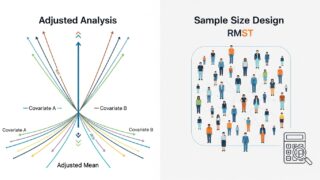医薬品の製造販売後調査においての例数の求め方

記事の目次
Toggleはじめに
製造販売後調査(Post-Marketing Surveillance:PMS)は、医薬品が承認され実際の臨床現場で使用される段階で、安全性・有効性に関する追加情報を収集するために実施されます。
その中でも、「どれだけの症例数を集めればよいのか」というサンプルサイズ設計は、実務者が必ず直面する重要テーマです。
しかし、PMS の例数設計は、治験のように明確な仮説検定に基づくものとは異なり、目的に応じて複数の考え方が存在するため、初学者には分かりにくい部分もあります。
この記事では、製造販売後調査での例数設計の考え方を整理します。
製造販売後調査における例数設計の特徴
PMS の例数設計は、治験と比べて次のような特徴があります。
| 項目 | 治験 | PMS |
| 主目的 | 有効性・安全性の検証 | 安全性の把握(特に稀な副作用) |
| 統計的枠組み | 仮説検定(有意差) | 発現率推定、リスク把握 |
| 例数の決め方 | α・β・効果量に基づく | 発現率の推定精度、稀な事象の検出確率 |
PMS では、「どれくらいの症例を集めれば、特定の副作用を一定の確率で検出できるか」という考え方が中心になります。
基本となる2つのアプローチ
PMS の例数設計は、主に次の2つのアプローチで考えられます。
① 発現率の推定精度に基づく方法(信頼区間アプローチ)
副作用の発現率 p を、ある精度で推定したい場合に用います。
② 稀な副作用の検出確率に基づく方法(Poisson/二項分布アプローチ)
「発現率が p の副作用を、少なくとも1例は検出したい」という考え方です。
以下で順に解説します。
発現率の推定精度に基づく例数設計
副作用の発現率 p を、誤差幅 d 以内で推定したい場合、二項分布の正規近似を用いて次の式が使われます。
基本式(95%信頼区間)
\[n=\frac{Z_{0.975}^2\cdot p(1-p)}{d^2}\]
ここで
- n:必要症例数
- p:想定される発現率
- d:許容誤差(例:±1% → 0.01)
- \(Z_{0.975}=1.96\):95%信頼区間の上側パーセント点
発現率 5% の副作用を ±2% の精度で推定したい
\[n=\frac{1.96^2\cdot 0.05(1-0.05)}{0.02^2}\]
計算すると、
\[n\approx 456\]
つまり、約450例が必要となります。
誤差幅を半分にすると、必要例数は約4倍になります。
PMS では、現実的な登録可能数とのバランスが重要です。
稀な副作用の検出確率に基づく例数設計
「発現率が p の副作用を、少なくとも1例は検出したい」という場合、二項分布を用いて次の式が使われます。
発現度数Xに二項分布を仮定して、
$$
\begin{align}
P(X \geq 1) = 1 – P(X=0)
&= 1 – \binom{n}{0}p^0(1-p)^{n-0}\\
&= 1 – (1-p)^n
\end{align}
$$
と導かれます。これを95%の確率で検出するには、
$$
\begin{align}
1 – (1-p)^n = 0.95 \\
(1-p)^n = (1-0.95)\\
nlog(1-p) = log(1-0.95)\\
n = \frac{log(1-0.95)}{1-p}
\end{align}
$$
となります。
例:発現率 0.1%(1/1000)の副作用を95%の確率で検出したい
\[p=0.001,\quad \beta =0.05\]
\[n\geq \frac{\ln (0.05)}{\ln (1-0.001)}\]
計算すると、
\[n\approx 2995\]
つまり、約3000例が必要となります。
実務でよく使われる「経験則」
日本の PMS では、次のような経験則がよく用いられます。
- 発現率 1% 程度の副作用 → 300例程度
- 発現率 0.1% 程度の副作用 → 3000例程度
- 発現率 0.01% 程度の副作用 → 30,000例程度
これは前述の「検出確率アプローチ」に基づくものです。
実務での例数設計の流れ
PMS の例数設計は、次のステップで進めると整理しやすくなります。
① 調査目的の明確化
- 安全性の把握か
- 特定の副作用の検出か
- 発現率の推定か
- 使用実態の把握か
目的により例数設計の考え方が変わります。
② 想定される発現率の設定
- 治験データ
- 文献
- 類薬の PMS データ
- 市販後の自発報告
これらを参考に、想定発現率 p を設定します。
③ 必要な精度・検出確率の設定
- 発現率推定 → 誤差幅 d
- 稀な事象検出 → 検出確率 1-\(\beta\)
④ 数式に基づく例数計算
前述の式を用いて計算します。
⑤ 実現可能性の評価
- 登録可能施設数
- 対象患者数
- 調査期間
現実的に達成可能かを検討します。
⑥ 規制当局との合意形成
PMDA との相談を通じて、例数の妥当性を確認します。
例:実際の PMS 例数設計(モデルケース)
- 想定副作用:肝機能障害
- 想定発現率:0.5%
- 95%の確率で1例以上検出したい
\[p=0.005,\quad \beta =0.05\]
\[n\geq \frac{\ln (0.05)}{\ln (1-0.005)}\]
\[n\approx 598\]
よって、約600例が必要と判断されます。
例数設計における注意点
- 治験データの発現率は市販後で変わることがある
市販後は患者背景が多様化し、発現率が上昇することもあります。 - 稀な事象は例数を増やしても検出できないことがある
発現率が 1/100,000 など極めて低い場合、PMS では検出が困難です。 - 実現可能性とのバランスが重要
理論上は数万例必要でも、実務上は不可能な場合が多いです。
まとめ
医薬品の製造販売後調査における例数設計は、治験とは異なる目的と考え方に基づいて行われます。治験では仮説検定に基づく有効性・安全性の検証が中心ですが、PMS では主に「安全性情報の把握」や「稀な副作用の検出」が目的となるため、例数設計も発現率の推定精度や検出確率に基づく方法が用いられます。
発現率の推定を目的とする場合には、二項分布の正規近似を用いた信頼区間の幅から必要症例数を算出します。一方、稀な副作用を一定の確率で検出したい場合には、二項分布(または Poisson 分布)を用いて「少なくとも1例を検出できる確率」を基準に例数を求めます。これらの式から、発現率が低いほど必要症例数が急激に増加することが分かり、実務上の大きな制約となります。
また、PMS の例数設計では、理論的な計算だけでなく、実際に登録可能な患者数や調査期間、施設数といった現実的な要因も重要です。必要例数が数千〜数万例となる場合もありますが、実務上達成が困難なケースも多く、規制当局との相談を通じて妥当な例数を設定することが求められます。
このように、製造販売後調査の例数設計は、統計的な根拠と実務的な制約の両面を考慮しながら、調査目的に応じて柔軟に設計することが重要です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4aa03195.892069bb.4aa03196.39df6be9/?me_id=1213310&item_id=18608225&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0844%2F9784860790844.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)